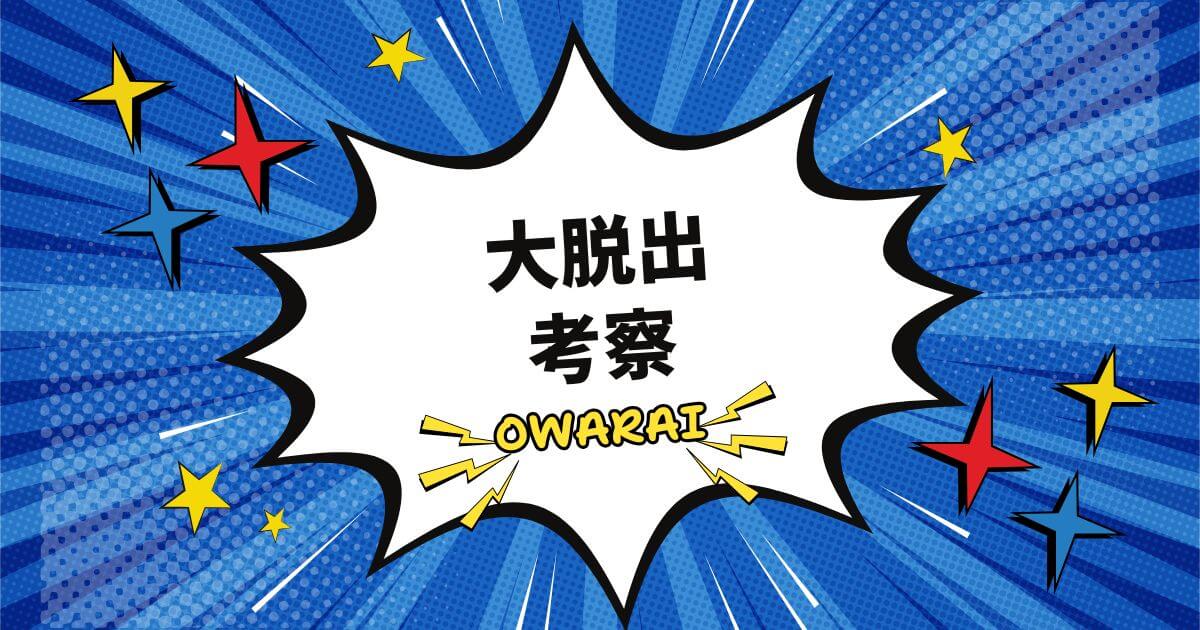DMM TV発のオリジナルバラエティ『大脱出』をご存じでしょうか?
この番組は、お笑い芸人たちが様々な異常状況に閉じ込められ、謎解きやチャレンジを駆使してそこからの脱出を目指すという構成になっています。
「大脱出には社会的な意味があるの?」「なぜあれほど過激な内容が可能なのか?」と疑問に思っている方も多いでしょう。
本記事では、『大脱出』シリーズ全体を対象に、ストーリー展開の考察と、社会的なメタファーとしての側面に焦点を当てて徹底分析します。
『大脱出』の考察ポイント
- シリーズ全体の構成とテーマの特徴
- 登場人物や設定に込められた象徴性
- 現代社会への批評性・風刺と示唆される問題意識
- 視聴者へのメッセージと解釈の余地
最後まで読めば、『大脱出』が単なる過激バラエティではなく、現代社会を映し出す鏡であり、深い考察に値する作品であることが理解できるでしょう。
140,000本以上が見放題
お笑い好きなら、DMM TVは必須!
注目の若手芸人が登場する番組から、佐久間宣行プロデュース作品まで爆笑必須の作品が多数。
まだチェックしていないあなたは今すぐチェック!
▼ 無料14日間体験&月額550円(税込)の圧倒的コスパ ▼
【「鬼」オモロイ注目作品!】
- 大脱出シリーズ:神の中の神番組!100回以上見るべし
- レンタルクロちゃん:まぁ面白い。フツーに面白い
- The Seat Out〜追放し合う女たち〜:良い。
- 月ともぐら:モグライダーの神番組!
- 会うもの全てを笑わせる!Everytime芸人
※ 変更の可能性もありますので、最新の状況はDMM TVでチェック!

シリーズ全体の構成とテーマの特徴
DMM TV発のオリジナルバラエティ『大脱出』は、地上波では実現不可能なスケールと過酷さを追求した脱出シリーズです。
藤井健太郎氏の手による本作は、お笑い芸人たちが様々な異常状況に閉じ込められ、謎解きやチャレンジを駆使してそこからの脱出を目指すという基本構成になっています。
このシリーズの特徴や基本構成について詳しく見ていきましょう。
- 連続ドラマのような物語性
- デスゲームさながらのコンセプト
- 地上波ではできないことを実現
- 金銭要素と人間の欲望
それぞれ詳しく解説していきます。
連続ドラマのような物語性
『大脱出』の大きな特徴は、連続ドラマのように物語性を持たせたシリーズ構成であることです。
シーズン1(全6話)・シーズン2(全7話)それぞれが一つの大脱出ストーリーとして完結する構成になっており、通常のバラエティ番組では各回完結が多い中、『大脱出』は独自の路線を歩んでいます。
藤井健太郎氏自ら「全話を通して観るものなのでストーリーがあるものにした」と語っており、視聴者がエピソードを重ねて味わうカタルシス(爽快感)を重視しているようです。
- 通常のバラエティと違い、各回完結ではない
- シーズン1は全6話、シーズン2は全7話の構成
- 伏線が回収される物語性を持った展開
この物語性のある構成が、視聴者に「次はどうなるのか」という好奇心を掻き立て、シリーズ全体の魅力を高めています。
伏線を回収する喜びや物語のカタルシスを味わえる点は、単なるバラエティ番組としては異色の要素と言えるでしょう。
デスゲームさながらのコンセプト
『大脱出』の物語は、「芸人が閉ざされた空間から、限られた情報をヒントに脱出する」というデスゲームさながらのコンセプトで構成されています。
シンプルな基本設定のもと、その中に数々のトリックや難題が仕掛けられており、視聴者は芸人たちと共に謎解きに挑むような感覚を味わうことができます。
シーズン1では様々なシチュエーションが同時進行で描かれ、これらが交互にカットバックされながら最終的に一つの脱出劇に収束するという構成が取られました。
- シーズン1:首まで土中に生き埋め、お菓子の家、電話でクイズ解答など
- シーズン2:再び生き埋め、クレーンゲーム、巨大ドミノ倒し、サイコロチャレンジなど
- 複数のミッションが最終的に一つの脱出劇として収束
このように複数のシチュエーションを組み合わせることで、予測不能な展開とストーリーの複雑さを演出しています。
シーズン2ではさらにスケールが拡大し、新たな参加者を加えてより過酷で奇想天外な課題が次々と登場します。
地上波ではできないことを実現
『大脱出』は、テレビ業界の延長線上にありながらも、地上波ではできないことばかりを実現することを狙った挑戦作です。
藤井健太郎氏はかねてより「クロちゃんを首まで埋める」という過激な企画を温めていたものの、地上波ではコンプライアンス上困難だったと語っています。
その封印されたアイデアに肉付けをして物語性を持たせたのが『大脱出』であり、シーズン1第1話からクロちゃんを土に生き埋めにするというインパクト重視の演出で幕を開けるという衝撃的な内容になっています。
- 地上波では規制されるような過激な演出を実現
- 「地味なルール違反を重ねている」と藤井健太郎氏自身が語る挑戦性
- コンプライアンスの壁を超えた表現の自由
藤井健太郎氏自身、「いわゆる地上波NGではなく、地味なルール違反を重ねているだけなので分かる人にしか分からないものだ」と述べており、過激さの中にも巧妙さを潜ませた作りになっているのだとか。
各所に謎めいた伏線や仕掛けをちりばめながら、バラエティでありながら連続ドラマ的な先が気になる構成を成立させている点も画期的です。
金銭要素と人間の欲望
シーズン2では、各脱出パートに「金銭」という要素が導入されたことも特筆すべきテーマ上の特徴です。
閉じ込められた部屋ごとに札束が置かれ、出演者はそれを消費しながら(=使い潰しながら)脱出を目指すという新たな駆け引きが加わりました。
単なる物理的脱出ゲームに留まらず、目の前の大金をどう扱うかという人間の欲望や葛藤を描く要素が入ったことで、笑いだけでなく社会実験的な面白さも増しています。
- 部屋ごとに置かれた札束を使いながら脱出を目指す
- 金銭の使い方に関する判断が求められる
- 欲望と脱出成功のジレンマを演出
この金銭要素により、出演者たちの心理的な葛藤やグループ内での意思決定プロセスが浮き彫りになります。
過酷な状況下で理性と欲望のせめぎ合いをどう演出しコントロールするかという点に、製作側の高度な意図が感じられますね。
▼ 無料14日間体験&月額550円(税込)の圧倒的コスパ ▼
【「鬼」オモロイ注目作品!】
- 大脱出シリーズ:神の中の神番組!100回以上見るべし
- レンタルクロちゃん:まぁ面白い。フツーに面白い
- The Seat Out〜追放し合う女たち〜:良い。
- 月ともぐら:モグライダーの神番組!
- 会うもの全てを笑わせる!Everytime芸人
※ 変更の可能性もありますので、最新の状況はDMM TVでチェック!

登場人物や設定に込められた象徴性
『大脱出』シリーズに登場する芸人たちは、それぞれ個性的なキャラクターと役割を担い、その存在自体が象徴的な意味合いを帯びています。
単なる出演者として描かれるだけでなく、彼らの行動や立場そのものが現代社会の縮図のように機能している面もあります。
ここでは、登場人物たちの象徴性と設定に込められた意味について考察してみましょう。
- クロちゃんという人柱の象徴性
- トム・ブラウンと「お菓子の家」の寓意
- さらば青春の光のヒーロー性
- シンボリックな設定の数々
それぞれ詳しく解説していきます。
クロちゃんという人柱の象徴性
シリーズの顔とも言えるクロちゃん(安田大サーカス)は、番組内で人柱的なキャラクターとして象徴的に扱われています。
シーズン1・2を通じて「首から下を生き埋めにされた状態で単独脱出を試みる」という最も過酷なポジションを任され、文字通り見せしめのような存在として描かれていました。
クロちゃんは以前から『水曜日のダウンタウン』等でも悪役芸人としてドッキリや罰ゲームの餌食になることが多く、『大脱出』での彼の存在は理不尽な目に遭わされる者の象徴となっています。
- 首だけ地表に出された姿が「見せしめ」を象徴
- 極限状態で見せる人間性がリアルに描かれる
- 苦境を笑いに変える芸人魂の体現者
興味深いのは、そのクロちゃんが極限状態で見せる人間性。
例えばシーズン1・2を通じて、彼が埋められた中で唯一楽しみにしていたのが「おしっこを漏らす瞬間」だったという告白は、究極状況下での人間の順応ぶりと滑稽さを象徴しています。
トム・ブラウンと「お菓子の家」の寓意
シーズン1ではトム・ブラウン(布川・みちお)の2人がおとぎ話のような「お菓子の家」に閉じ込められるという設定が用いられました。
この設定には深い寓意が込められており、お菓子の家というファンシーな空間が実は脱出すべき牢獄であるというギャップが特徴です。
このシチュエーションは「快楽や誘惑が罠となる」ことを示唆しており、突飛な笑いの中にも寓話的な意味を感じさせます。
- お菓子の家は甘美な誘惑のメタファー
- 童話『ヘンゼルとグレーテル』を彷彿とさせる構図
- 一見楽しそうな環境が実は牢獄であるという皮肉
トム・ブラウンのみちおは巨体と奇声で知られる異色芸人ですが、そんな彼が甘い家から脱出する様子はまるでおとぎ話の怪物が知恵を絞って解放に至るようなユーモラスな寓意を帯びています。
実際に彼らは食べられる壁やお菓子に囲まれつつも、そこから抜け出す方法を探さねばならず、この矛盾がストーリーに深みを与えているのです。
甘いものに囲まれた環境が実は脱出すべき場所という逆説は、現代社会の消費文化に対する皮肉にも感じられますね。
さらば青春の光のヒーロー性
シーズン2で特に象徴的役割を果たすのがさらば青春の光の森田哲矢・東ブクロのコンビ。
彼らは「クイズの答えを電話で聞き出す密室」に閉じ込められ、自力で脱出可能な最初の関門を突破した後、他の芸人たちを助けるため積極的にコミュニケーションを図る立場に回りました。
最初は理不尽な状況に腹を立てストレスを募らせていた彼らですが、次第に今回の大脱出全体の構造や自分たちの使命に気付き、リーダーシップを発揮していきます。
- 自力脱出から他者救済へと成長するヒーローの旅
- 物語の「主人公」的存在へと変化
- 利己的なサバイバルから利他的な連帯への移行
この過程は、彼らが単なる参加者から物語の「主人公」的存在へと成長していく様子として描かれており、まさに『ヒーローのメタファー』です。
森田・東ブクロの二人は実生活では過去の不祥事や確執を乗り越えて再起した経緯を持つコンビですが、本作でも「仲間と協力し全員で脱出しようと奔走する」姿が強調されます。
彼らの姿は「利己的なサバイバルから利他的な連帯へ」というテーマを体現しており、現代社会におけるリーダーシップのあり方を示唆しているようにも感じます。
シンボリックな設定の数々
『大脱出』の様々な設定にもシンボリックな要素が見られます。
例えば「クレーンゲームで取れた景品を使って脱出」という課題では、運や器用さといった要素が試されるだけでなく、クレーンゲームという消費社会的アイコンが登場します。
これは「娯楽や運試しが生死を分ける」皮肉な構図であり、景品=命綱という逆転したシンボルです。
- クレーンゲームは消費社会の象徴が生死を分ける皮肉
- ドミノ倒しは「一人のミスが全体に波及する」社会の縮図
- 札束は「欲望」と「取引」の象徴として機能
また「部屋全体でのドミノ倒しを成功させて脱出」では、全員の連携と慎重さが求められるため、一人のミスが全体に波及する様子をドミノに喩えて見せています。
ドミノ倒しの連鎖はそのまま共同体や社会の繋がりのメタファーであり、芸人たちが緊張感の中で協力するシーンに象徴性を与えているように読み取れます。
シーズン2の新要素であった札束の存在は、言うまでもなく「欲望」や「取引」の象徴であり、まさに人間の本性を暴く仕掛けになっているわけですね。
▼ 無料14日間体験&月額550円(税込)の圧倒的コスパ ▼
【「鬼」オモロイ注目作品!】
- 大脱出シリーズ:神の中の神番組!100回以上見るべし
- レンタルクロちゃん:まぁ面白い。フツーに面白い
- The Seat Out〜追放し合う女たち〜:良い。
- 月ともぐら:モグライダーの神番組!
- 会うもの全てを笑わせる!Everytime芸人
※ 変更の可能性もありますので、最新の状況はDMM TVでチェック!

現代社会への批評性・風刺と示唆される問題意識
『大脱出』シリーズは一見するとただの過激なお笑いバラエティですが、その背後には現代社会への風刺やメタな批評性が随所に込められていると解釈できます。
製作者の意図や構成には、私たちの社会が抱える様々な問題や矛盾を鏡のように映し出す側面があります。
ここでは、作品に込められた社会批評的な要素や問題意識について深く掘り下げていきます。
- テレビ業界への批評
- 競争社会と欲望のメタファー
- メディアの虚実を問いかける視点
- 芸人という職業への批評
それぞれ詳しく解説していきます。
テレビ業界への批評
『大脱出』の企画背景には、テレビ業界の閉塞感に対する一種の脱出という意味合いがあります。
藤井健太郎氏自身、「ずっとやりたかったアイデア」が地上波では放送できずDMM TVでようやく実現できたと明かしていました。
本作はテレビ業界の延長線上にありながらも、地上波ではできないことばかりを実現することを狙った挑戦作であり、それ自体がテレビの現状への風刺となっています。
- 地上波のコンプライアンスへの批判的視点
- 「地味なルール違反を重ねる」という挑戦的姿勢
- 視聴者の「これこそ見たかった」という欲求に応える姿勢
地上波ではNGとされるような企画をネット配信ならではの自由さで通し、視聴者に「これこそ見たかった刺激だ」と思わせたこと自体が、テレビの現状への挑戦的メッセージと言えます。
実際、視聴者の中には「DMM TVはこの路線を大事にすればファンを掴める」と評価する声もあり、保守的になりがちなマスメディアに対するアンチテーゼとして本作が受け止められている面があります。
競争社会と欲望のメタファー
本作の根幹にある「デスゲーム」「密室からの生還」というモチーフ自体が、現代社会への寓意として読み取れます。
デスゲーム作品は往々にして競争社会や格差、監視体制などのメタファーを含んでいますが、『大脱出』はそれをお笑いに転化することで逆に現実のシビアさを浮き彫りにしている部分があります。
特にシーズン2で「欲望」というテーマが社会批評的に扱われており、各部屋に置かれた札束が芸人たちの判断を揺さぶる場面は印象的でした。
- デスゲーム=競争社会のメタファー
- 札束を前にした芸人たちの反応=資本主義社会の縮図
- 自己保身と仲間意識の衝突という普遍的テーマ
例えば、シーズン2で森田・東ブクロらが自分だけ助かる選択を捨て、他者と協力する道を選んだ展開は、競争社会の中で利他性やチームワークを選ぶことの尊さを示唆しているようにも見えます。
一方、芸人のみなみかわが「僕、先に出ていいですか?」と口にした際に他の仲間から「いいわけがないだろう!」と一喝される場面は、自己保身と仲間意識の衝突という普遍的なテーマを描いています。
メディアの虚実を問いかける視点
本作はメディアの虚実についてのメタ視点も提供しているように感じます。
番組はドキュメンタリー風のタッチを装いつつも所々に演出臭さがあり、一部視聴者から「途中で台本が見えて冷めた」との指摘も受けました。
しかし別の見方をすれば、これは「バラエティとは虚構と現実の狭間を楽しむもの」だという暗黙の了解を提示しているとも言えます。
- ドキュメンタリーとフィクションの境界を曖昧にする演出
- 「モキュメンタリー」として虚実のバランスを楽しむ視点
- メディアリテラシーと遊び心の両立
製作者側も視聴者も、完全なガチンコのサバイバルでないことは承知の上で、それでもなおスリルと笑いに興奮する、現代のリアリティショーやドキュメンタリーが孕む構造を本作は内包しています。
実際、あるレビューでは『大脱出』を「謎解きをしている芸人たちのリアクションを楽しむモキュメンタリー(疑似ドキュメンタリー)」と位置づけ、「嘘を笑って楽しむくらいがちょうどいい」と喝破しています。
『大脱出』は観客に「これはバラエティだ」と開き直らせ、エンタメの嘘と真実を両方楽しませる仕組みになっているのかもしれません。
芸人という職業への批評
「芸人という職業」そのものへの批評も『大脱出』には感じられます。
日本のお笑い芸人は身体を張った芸が美徳とされる文化がありますが、『大脱出』はその最たる極限を見せつけています。
レビューでも「日本のお笑い芸人にしかできない、させてはいけない、本当に理不尽で理由のわからない状況」が次々降りかかり、それを芸人たちは「美味しく」(=笑いに変えて)切り抜けていくと評されてる声も多数。
- 身体を張るお笑い文化の極限形態
- 笑いと倫理のギリギリの線を攻める表現
- エンターテイナーのプロ根性と犠牲の両面
これは観る側にとって爆笑であると同時に、「こんな仕事を強いられる芸人って大丈夫なのか?」という薄氷の上の倫理観を突きつけてもいます。
極限状態に置かれた芸人たちがそれでもカメラの前で笑いを取ろうとする姿は、エンターテイナーのプロ根性への賛美であると同時に、その裏側にあるかもしれない犠牲や狂気への皮肉な眼差しでもあるのです。
笑いと倫理のギリギリの線を攻めることで、お笑い業界の光と影を私たちに意識させる効果があるようにも感じます。
▼ 無料14日間体験&月額550円(税込)の圧倒的コスパ ▼
【「鬼」オモロイ注目作品!】
- 大脱出シリーズ:神の中の神番組!100回以上見るべし
- レンタルクロちゃん:まぁ面白い。フツーに面白い
- The Seat Out〜追放し合う女たち〜:良い。
- 月ともぐら:モグライダーの神番組!
- 会うもの全てを笑わせる!Everytime芸人
※ 変更の可能性もありますので、最新の状況はDMM TVでチェック!

視聴者へのメッセージと解釈の余地
『大脱出』シリーズは単なる過激なお笑い番組ではなく、視聴者に様々なメッセージを投げかけ、多様な解釈の余地を残しています。
番組の内容やテーマ、芸人たちの行動を通して、視聴者は様々な角度からこの作品を読み解くことができます。
ここでは、『大脱出』が視聴者に投げかけるメッセージや解釈の可能性について考察します。
- 逆境を乗り越えるポジティブメッセージ
- 多様な解釈の余地
- 視聴者との一体感の創出
- お笑いへのリスペクトとエール
それぞれ詳しく解説していきます。
逆境を乗り越えるポジティブメッセージ
『大脱出』シリーズが視聴者に投げかけるメッセージは、一義的には「どんな逆境でも諦めずに知恵と力を振り絞れば活路は開ける」というポジティブなものです。
番組内で提示されるルールはシンプルで、「何が何でも脱出せよ」ただ一つ。
絶対的なミッションを前に、出演者たちが文句を言いながらも最終的には己の持ち味と協力で課題をクリアしていく様子は、困難に立ち向かう勇気や創意工夫の大切さを笑いを交えて伝えているように映ります。
- 絶対的な困難に対して諦めない姿勢を示す
- 協力して問題を解決する重要性
- 「人は極限でこそ真価を発揮する」というメッセージ
実際、シーズン2では出演芸人全員が揃って脱出を成し遂げますが、その直前に見せた常人には到底真似できないような狂気の行動によって視聴者は「彼らはこうして生き残ってきたのか…」と圧倒される展開になりました。
それは同時に、「人は極限でこそ真価を発揮する」「仲間と力を合わせれば不可能も可能にできる」というメッセージとして心に刻まれます。
多様な解釈の余地
『大脱出』には多様な解釈の余地が用意されています。
バラエティとして腹を抱えて笑うのも良し、社会風刺として読み解くのも良し、エンタメ作品としてストーリー性を追うのも良しと、受け手によって感じ取るポイントが変わるのも『大脱出』の魅力です。
ある視聴者は最終話のワンシーンで感動のあまり涙を流し、隣で観ていた奥さんに「何で泣いてるの?」と不思議がられたそうですが、それほどまでにこの番組は笑い以上のものを見る人に与え得るのです。
- 純粋にお笑いバラエティとして楽しむ視点
- 社会風刺として読み解く批評的視点
- 人間ドラマとして感情移入する視点
涙の理由は、人によって「芸人たちの頑張りに胸を打たれた」「自分にはできないことをやり遂げる姿に感動した」「過酷な道のりを経て得たラストのカタルシスに心震えた」と様々でしょう。
しかしいずれにせよ、本作が単なるお笑いではなく一つの人間ドラマとして受け取られたことの証でもあります。
視聴者との一体感の創出
『大脱出』は視聴者との一体感を生むことにも成功しています。
スタジオで見届け人を務めるバカリズムや小峠英二(バイきんぐ)は、視聴者目線でVTRにツッコミを入れたり驚いたりする役割ですが、そのリアクションが的確で「見ていて心地いい」との評価もありました。
彼らを通じて視聴者はまるで自分もその場で一緒に見守っているかのような感覚を味わい、極限の密室に閉じ込められた芸人 vs. それを安全圏から眺める視聴者という構図自体も、実は巧みに設計されたものです。
- スタジオ出演者が視聴者の代弁者となる構造
- 安全圏から「ハラハラ」を楽しむ視聴体験
- 視聴者も脱出ゲームの参加者になれる仕掛け
視聴者は彼らに感情移入し応援しつつも、自分は安全な場所で見物しているという優位な立場にもいます。
そのため適度な安心感の中でハラハラを楽しむことができ、エンタメとしてのカタルシスが倍増していると言えるでしょう。
ある意味、視聴者自身も脱出ゲームの参加者であり、最終回で全員が脱出できたときには我がことのように爽快感を味わえる、そのような巻き込み型のメッセージ性も秘められています。
お笑いへのリスペクトとエール
最後に、本作はお笑いに対するリスペクトとエールを込めた作品でもあります。
藤井健太郎氏は数多のバラエティで実績を上げてきた名手ですが、本作では特に芸人たちのポテンシャルを信頼し最大限に引き出しています。
シーズン2ではさらば青春の光の二人に全幅の信頼を置いて物語を託した節があるとも評され、実際に彼らは期待以上の活躍で応え、視聴者に「この芸人はこんな一面があるのか」という新たな発見を提供しました。
- 芸人たちの隠れた素質や魅力を引き出す構成
- 過酷な状況でも笑いを届ける職業へのリスペクト
- 視聴者に芸人への新たな評価を促す
エンタメ評論の観点から見ても、全出演者がそれぞれの個性と見せ場を発揮しており、「全員がかっこよくて最高だった」との声も上がっています。
これはつまり本作が芸人たちへの賛辞、ひいては視聴者への「彼らをもっと応援したいと思わせる」メッセージになっているのです。
▼ 無料14日間体験&月額550円(税込)の圧倒的コスパ ▼
【「鬼」オモロイ注目作品!】
- 大脱出シリーズ:神の中の神番組!100回以上見るべし
- レンタルクロちゃん:まぁ面白い。フツーに面白い
- The Seat Out〜追放し合う女たち〜:良い。
- 月ともぐら:モグライダーの神番組!
- 会うもの全てを笑わせる!Everytime芸人
※ 変更の可能性もありますので、最新の状況はDMM TVでチェック!

まとめ:社会を映す鏡としての『大脱出』
DMM TVオリジナル『大脱出』シリーズは、過酷な脱出ゲームとお笑いを融合させた意欲作です。
一貫したテーマと進化する仕掛けで視聴者に笑いとスリルと感動を提供する本作の裏側には、メディア批評や社会風刺の要素が織り込まれています。
藤井健太郎氏の演出力と芸人たちの奮闘ぶりが高く評価され、「地上波の常識を超えた異色バラエティ」として成功を収めました。
単なる過激企画ではなく、現代社会への洞察を含んだエンターテインメントとして、今後の展開にも大きな期待が寄せられています。
『大脱出』考察のポイント
『大脱出』は単なる過激バラエティではなく、社会批評の側面を持った作品です。物語構造の特徴、クロちゃんをはじめとする出演者の象徴性、現代社会への風刺、そして視聴者へのメッセージなど、多角的な考察が可能な奥深いコンテンツとなっています。テレビ業界の常識からの脱出とも言える本作は、新しいエンターテインメントの可能性を示しています。
140,000本以上が見放題
お笑い好きなら、DMM TVは必須!
注目の若手芸人が登場する番組から、佐久間宣行プロデュース作品まで爆笑必須の作品が多数。
まだチェックしていないあなたは今すぐチェック!
▼ 無料14日間体験&月額550円(税込)の圧倒的コスパ ▼
【「鬼」オモロイ注目作品!】
- 大脱出シリーズ:神の中の神番組!100回以上見るべし
- レンタルクロちゃん:まぁ面白い。フツーに面白い
- The Seat Out〜追放し合う女たち〜:良い。
- 月ともぐら:モグライダーの神番組!
- 会うもの全てを笑わせる!Everytime芸人
※ 変更の可能性もありますので、最新の状況はDMM TVでチェック!